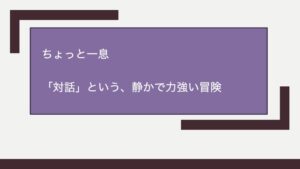娘がまだ幼かった頃、年始の音楽発表会が恒例行事でした。 発表が終わるとすぐに、次の楽譜が手渡されます。 渡された譜面には、おたまじゃくしがびっしり。「えっ、こんな曲、私に弾けるの?」 娘は不安そうな表情を浮かべるのですが、やがて1小節、また1小節と、毎日の練習の中で音がつながっていく。 気がつけば、1曲が完成していました。もちろん、母親として毎日伴走しています。 彼女は何度も、「できないと思っていたけれど、できるようになった」経験を積んできました。
努力の積み重ねは、評価や結果とは別の次元で、“自分との信頼”を育てるのだと、私は思います。
自己肯定感とは、“できなさ”を知ることから始まる
「自己肯定感が大切」と言われる時代です。 稚拙な言葉を使うとすれば「ありのままの自分」を認めることでもあるのですが、私は、どこかひっかかりを覚えることがあります。 まるで、変わらなくていい、成長しなくてもいい、という免罪符のように使われてしまうことがあるからです。
私が考える自己肯定感とは、きっと「自分の弱さも知っていること」。 できない部分を見ないふりするのではなく、「できない」と言える勇気や、それでもやってみようと思える力。 その土台があってこそ、「自分を信じて進む」ことができるのことだと考えています。
外からの評価ではなく、自分との約束が自信になる
娘が通っていたシドニーの学校で、バイオリン演奏の機会がありました。 日本では当たり前だった音楽のレベルが、海外では予想外の賞賛を受けたのです。 その時の娘の表情は、今も忘れられません。誰かに忖度されるのではなく、“純粋なまなざし”で認められること。 それは、自分の内側から「やってきてよかった」という確かな感覚につながったようでした。(※注意 レベルとは、日本でも海外でも、あくまでも私たち家族が置かれた社会でのレベルを指します)
一方で、母親である私は長年、自信が持てずにいました。 「どうしてそんなに自信がないの?」とパートナーに言われるたびに、言葉に詰まりました。 思い返せば、私はいつも「誰かと比べられる世界」に生きていたのだと思います。 田舎の小さな村、家族、親戚、近所…“世間の目”が自分の評価を決めていた。 そしてその評価が、自分の価値を決めると思い込んでいました。
子どもに託した“自分の願い”は、悪いことだけではなかった
だからこそ、娘には「世間の目」を気にしすぎるような子にはなってほしくない、という思いがありました。 それは親の願望であり、ある意味では「価値観の投影」だったかもしれません。 でも、結果的には彼女にとって、「できないと思っていたことに向き合う力」を育む機会になっていたように思います。
声かけ一つをとっても、私は変わりました。 「すごいね」「えらいね」という結果に対する言葉よりも、 過程や努力に目を向ける言葉を意識して使うようになりました。
組織でも同じ──成果だけでなく、プロセスに目を向ける育成を
人材育成の現場でも、「成果」ばかりにフォーカスが当たると、 結果を出せなかった人は「自分には価値がない」と思い込んでしまいます。 でも、頑張っている姿勢や、目に見えない準備・下支えにも光を当てることで、 その人の「自分との信頼感」は、確実に育っていくのです。
仕事における自信形成も、実は同じ。 できない時期があっていいし、できないなりに進んでいる自分を、認められるような関係性が必要です。 自己効力感と自己肯定感は、一方通行の関係ではなく、挑戦と内省のプロセスの中で、何度も行き来しながら育っていく感覚があります。
最後に、あなたへの問い
あなたが育てたい「自信」とは、どんな自信ですか?
結果に左右されない自信とは、どんなプロセスから生まれると思いますか?
Stay tuned for the next article!